※この記事はプロモーションを含みます
「実家が片づかない」「子どもが片づけをしない」「気づけば自分のモノも増えてしまう」
──そんなふうに三方向からの“片付けの悩み”を抱えながら過ごす40代女性は少なくありません。
親世代は、思い出や物を大事にしてきたからこそ手放せない。
子ども世代は、物に囲まれていても“必要・不要”の判断が難しい。
そして40代の私たちは、親と子の両方に気を配りながら、自分自身の暮らしも整えなければならない立場。
「自分だけでは限界かも」 と感じることはありませんか?
この記事では、親・自分・子どもという三世代で無理なく協力しながら進める断捨離のコツをまとめました。
家族の会話が増え、空間が整い、心までラクになる──
そんな三世代で進める整理のヒントを、一緒に探してみませんか?
💡 こんなモヤモヤ、抱えていませんか?
- 親が「もったいない」と物を減らせない
- 子どもが片付けのやり方を知らず散らかす
- 自分自身も片付けが後回しになってイライラする
大丈夫、あなただけではありません。
この記事では、「親・自分・子ども」三世代で協力して進める片付けのコツを
具体的にお伝えします。
まずは、共感の多いこちらの記事もおすすめです↓
▶ 実家の片付けに悩むあなたへ“心の整理”の始め方
親世代の片付け・気持ちの整理
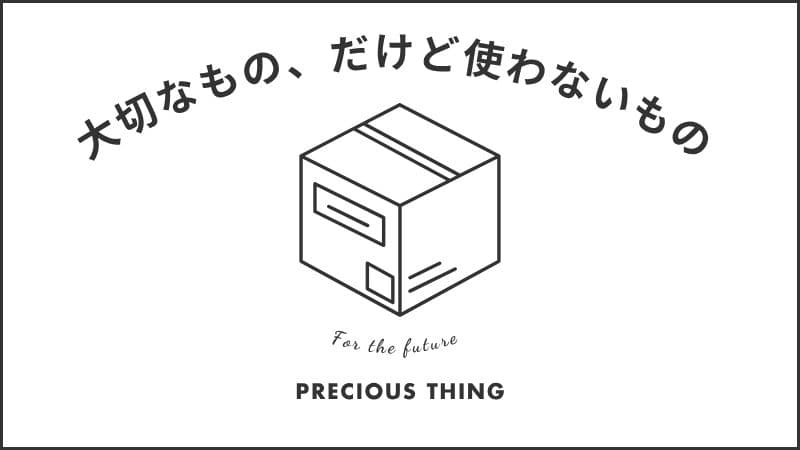
実家の片付けを始めると、親世代の「捨てられない思い」や、子世代の「忙しくて向き合えない事情」がぶつかり合い、進め方に悩むことも多いです。
さらに、私たち40代はちょうどその“真ん中の世代”。仕事や子育てに追われる中で、実家や家族の持ち物の整理に向き合う時間をどう作るかが課題になります。
ここでは、親・自分・子どもの三世代で無理なく整理を進めるための工夫をご紹介します。
- 親が捨てられない理由とその心理
- 親とケンカにならない声かけの工夫
- 思い出の品の残し方|まんてん録などのデジタル活用
- 親の代から受け継いだ「使わないモノ」どうする?|くらしのコンシェルジュ
親が捨てられない理由とその心理

「実家に行くとモノだらけで落ち着かない」
そんな感覚、意外と子どもも同じように抱えているものです。
親世代はモノを大切にしすぎて、なかなか手放せない。
「まだ使えるから」「誰かが欲しいかも」としまい込み、結果的に暮らしがぎゅうぎゅうになってしまう…。
特に祖父母世代は、戦後のモノが少ない時代を生きてきた背景から「捨てること=もったいない、申し訳ない」という気持ちを無意識に持っている方が多いです。
でも、散らかった空間は孫にとっても落ち着かず、集中しづらい場所になりがち。
「家族の空間をもっと心地よくするために」
──そう考えると、整理のきっかけをつくる価値は十分あります。
親とケンカにならない声かけの工夫

「これ捨てるの? まだ使えるのに!」
──親世代との片付けで、こんなセリフに戸惑った経験はありませんか?
親御さんにとっては、モノを手放すことが「もったいない」「申し訳ない」と感じる世代背景があり、なかなかすぐには受け入れられないものです。
そんなときは、
「誰が使うかな?」
「これは思い出として残しておこうか?」
など、親と一緒に“選ぶ時間”を持つのがおすすめ。
押しつけではなく“対話しながら選ぶ”ことで、感情のぶつかりを減らせます。
さらに「全部やろう!」ではなく「今日は玄関だけ」「まずは1段だけ」といった 小さな達成感 を積み重ねる工夫も、親子ともにストレスを減らすコツになりますよ。
思い出の品の残し方|まんてん録などのデジタル活用
「これは私の若い頃のアルバムなの」「この写真、孫にも見せたいわね」──そんな風に思い入れのある写真は、無理に処分しなくても大丈夫。
最近では、古い紙写真をスキャンしてデータ化してくれる「まんてん録」のようなサービスが登場しており、補正やスライドショー化、クラウド保存など、便利な機能が揃っています。
「場所を取るけれど捨てたくない」そんな悩みをスマートに解決してくれるだけでなく、デジタル写真がきっかけで会話が生まれたり、家族の記憶がよみがえることもあります。

昔のアルバムをデジタル化したら、思い切って整理できて心まで軽くなりました。親も喜んで「また見たいね」と言ってくれます。
(40代女性・3児の母)

色褪せや劣化が気になっていたけど、データなら安心。思い出が“守られている”感覚がうれしくて、もっと早く頼めばよかったです。
(40代・整理を始めたばかりの主婦)

最初は写真を送るのが不安でしたが、きちんと丁寧に扱っていただいて安心しました。スマホで簡単に見返せるようになり、母ともたくさん会話が増えました。
(50代女性・実家の整理中)
親の代から受け継いだ「使わないモノ」どうする?|くらしのコンシェルジュ
「いらないけど、自分では運べない…」
そんな大型家具や家電の処分は、《くらしのコンシェルジュ》のような不用品回収の一括見積サービスを活用すると手間なくスムーズです。
複数社の料金を比較できるので、最安値での依頼がしやすく、口コミ評価もチェックできるのがポイント。
価格だけでなく対応の丁寧さなども確認できるため、初めてでも安心して依頼できます。
- 使っていない家電 → 回収・下取りへ
- 着ない衣類 → リユースまたは素材として再活用
- 家具 → 不用品回収サービスで一括処分

実家の片付けでお願いしましたが、対応がとても丁寧で、親も安心して任せられました。比較して選べたのも助かりました。
(40代女性・フルタイム勤務)

回収業者ってちょっと不安だったけど、ここはしっかりしていて信頼感あり。複数社の中から納得いくところを選べたのでよかったです。
(40代主婦・2世帯同居)

使わなくなった婚礼家具を処分したくて《くらしのコンシェルジュ》に依頼。重いものでも対応が早くて、料金も比較して決められたので満足しています。
(50代女性・実家整理中)
\📦 手間なく片付く!不用品回収の一括見積比較はこちら/

40代ママの片付け・役割の整理
子どもがなかなか片付けてくれない…。
毎日バタバタで、自分の片付けどころか家の中もごちゃごちゃしてしまう…。
そんな悩みを抱える40代ママはとても多いです。
でも実は、子どもが片付けられないのは「やる気がないから」ではなく、「やり方がわからないから」かもしれません。
ここでは、親のちょっとした工夫で子どもが自然と片付けたくなる“仕組み”を一緒に考えていきましょう。
- 「自分のモノが増える理由」を見直す
- 家族に協力してもらう断捨離の進め方
- 子どもへの片付け声かけや役割分担のヒント
- 自分のタイミングで進める習慣化のコツ
「自分のモノが増える理由」を見直す
片付けが進まないのは、子どもだけが理由ではないかもしれません。
実は、私たちもつい「とりあえずとっておこう」とモノを増やしていることがあります。
・なんとなく取っておいた学校のプリントや仕事の書類
・お得だからと買ってしまったセール服
・思い出や記念の品
こうしたものが少しずつ積み重なって
家のスペースを圧迫して管理の負担を大きくしていくんです。
まずは自分の持ち物を振り返り、
「これ、本当に必要?」「誰が使う?」「この服着るかな?」と問い直すところからスタートしてみましょう。
家族に協力してもらう断捨離の進め方
片付けはひとりで頑張ると心が折れやすいものですよね。
だからこそ、家族にも協力してもらうことが大切です。
「使ってないもの、一緒に見直そうか」
「どれなら残したい?」
と声をかけて、“選ぶ作業”を家族で共有するイメージです。
押し付けではなく「一緒に決める」空気感を大事にするとストレスなく進めやすくなりますよ。
子どもへの片付け声かけや役割分担のヒント
子どもに「片付けて!」と何度言ってもなかなか動かない…。
それは「どうすればいいか」が分からないだけかもしれません。
例えば、
・ランドセルを置く場所を決める
・週末だけ一緒に片付けタイムをつくる
など“ルールと習慣”をセットで伝えるのがおすすめです。
また、「本をしまう係」「おもちゃを整理する係」など
役割分担を決めることで、子ども自身のやる気が高まりやすくなります。
大人も子どもも、人って役割を与えられるとなぜか頑張れますよね。
自分のタイミングで進める習慣化のコツ
「平日は時間がない」「週末は疲れて無理」
そんな声も多いですよね。
でも、ほんの5分でもOK。
「夕食の片付け後に10分だけ」「寝る前に1か所だけ」など、自分の生活の中で“習慣に組み込む”ことがコツです。
頑張りすぎなくても、少しずつ進めれば片付けが暮らしの一部として定着しやすくなります。
子ども世代の片付け習慣づくり
「また部屋が散らかってる…」「なんで出しっぱなしなの…?」
そんなふうに子どもの片付けに悩む40代ママ、多いですよね。
でも実は、ちょっとした声かけや仕組みづくりで子どもが自然に片付けできる環境をつくることができます。
ここでは、子どもの片付け習慣をサポートするコツを一緒に見ていきましょう。
片付けられないのは「やり方を知らない」から

「また出しっぱなし!」「どうして毎回ぐちゃぐちゃなの?」
──でもちょっと待って。子どもって、そもそも片付け方を教わっていないことが多いんです。
たとえば、「プリントは教科ごとにファイルへ」「文房具はトレーで仕切る」など、目的ごとに分けるルールを一緒に作るだけで、劇的に片付けやすくなります。
「今日は机の引き出しだけ」「10分だけ一緒にやってみよう」──そんな小さなステップから始めるのがコツです。
親の行動で伝える片付け習慣

「片付けなさい」と言うよりも、親自身が“日常的に片付けている姿”を見せること。
実はそれが、一番強く子どもに伝わる方法です。
「読み終わったら本棚へ」
「朝、服をしまってから出かける」
——そんな日々の動作が、子どもにとっての“当たり前”になります。
そして、自分の書類や写真、思い出の品がたまってきたときは、自分の断捨離を進めるチャンス。
写真などの紙モノは、デジタル化することで収納スペースを大幅に減らすことも可能です。
たとえば、古いアルバムや思い出写真を高解像度でスキャンし、色補正・スライドショー保存もできるサービスを活用すれば、
親子で思い出を見返す時間にもつながります。
🧠心理学でも証明された「親の行動」の影響力
子どもにとって一番の教材は、やっぱり親の“普段の姿”です。
実はこのこと、心理学の分野でも注目されています。
▶ NHK 番組ページを見る
たとえば、NHK『あしたが変わるトリセツショー』では、
「片づけ行動が脳と感情に与える影響」を取り上げており、
日常の整った環境が子どもの集中力や安定感に繋がると紹介されました。
▶ Amazonで書籍をチェックする
さらに、心理学者・鈴木宣之氏の著書『整理整頓の心理学』では、
片づけによって「自己管理能力」が育まれ、
計画性や思考の柔軟性にも良い影響があると解説されています。
こうしたデータからも、「親の片づけ習慣が子どもに伝わる」という考えは、
“気のせい”ではなく、しっかりと裏付けのある行動なのです。
📌子ども目線の収納・環境の工夫|SHIRAI STOREのマミハピシリーズ
片づけを「やる気」ではなく「やりやすさ」で解決するなら、収納の見直しが効果的。
とくに子どもには、「戻す場所が明確」「扱いやすい高さと構造」がポイントです。
たとえば、《SHIRAI STORE(シライストア)》のマミハピシリーズでは、ランドセルや教科書置き場を決めておくだけで、毎日の動きがスムーズに。
“自分でしまえる”収納があると、自然と習慣として身についていきます。
ある人気のシリーズでは、子ども目線の使いやすさとインテリア性の両立が追求されており、
おしゃれで実用的なキッズ収納として、親子に支持されています。

「片づけて〜!」と何度も言わなくなりました。子どもが自分で本を戻す姿に驚き。親も子もラクになりました。
(40代・小1のママ)

シンプルなデザインだから、成長しても長く使えそう。親子で選んで、子どもが率先して整理するようになったのが何より嬉しいです。
(40代・インテリア好きな主婦)

子ども部屋にSHIRAI STOREのマミハピ棚を置いてから、「片づけてから寝ようね」が自然に習慣に。親子でストレスが減りました。
(40代女性・共働きママ)
\ 人気のキッズ収納をSHIRAI STOREでチェックする/
三世代断捨離を成功させるコツ

「片付けが進まないのは私のせい?」
「親も子どもも思うように動いてくれない…」
そんな悩みを抱える方にこそ試してほしいのが“三世代で取り組む断捨離”です。
世代ごとに片付けへの価値観は違っても、行動を共にすることで会話が増えたり、思い出をシェアする時間が生まれたりと、心にも変化が生まれます。
ここでは、三世代で無理なく片付けを進めるためのポイントと、実際に「やってよかった!」という声をまとめてお伝えします。
役割分担の考え方
三世代で断捨離を進めるときに欠かせないのが、「どこを誰が担当するか」という役割分担です。
親には「捨てるか迷うものの確認」を、
自分は「仕分け・分別や粗大ゴミの手配」を、
子どもには「残すものをきれいに戻す」など、
それぞれの負担を小さくする工夫を取り入れましょう。
「全部自分でやらなきゃ」と抱え込まないことが成功のカギ。
それぞれの得意・不得意に合わせてうまく分担しながら進めると、家族全体のストレスも減らせますよ。
「一気にやらない」断捨離の進め方
一度に全部終わらせようとすると、
親も子どもも疲れてしまい、気持ちも折れがちです。
例えば、
・今日は玄関だけ
・週末はリビングだけ
・アルバムは冬休みに…
といったように、期間を分けて取り組むのがおすすめ。
「ここまでできたね」と達成感を家族で共有しながら進めると、
自然と次のステップにも前向きに取り組めますよ。
無理のないペースで続けられる仕組みを意識してみてくださいね。
体験談:三世代でやってよかった声

母と一緒に片付けるうちに、昔の思い出話もたくさんできて嬉しかったです。
モノだけじゃなくて心まで整理できた感じ!
40代・共働きママ

子どもが『自分の場所をきれいにするの楽しい』と言い出してびっくり。
最初は面倒くさそうだったのに、習慣づいたのが一番の収穫でした。
40代・パート勤務

祖母と娘、私の3人で思い出を確認しながら進められたのがよかった。
『捨てる』じゃなく『どう残すか』を一緒に考えられて気持ちがラクになりました。
40代・在宅ワーク

分担して進めたおかげで、結局ゴミも減らせたし
気持ちも軽くなった!最初から家族に任せる意識を持てばよかったです。
40代・フルタイム勤務

最初は祖母が捨てるのを嫌がってたけど、
“残す理由”を話してもらう中でお互い納得できる選び方が見つかりました。
子どもも参加できて思い出を大切にできたのが何よりです。
40代・自営業
心まで軽くなる!三世代断捨離のポイント総まとめ

3世代が協力しながら進める断捨離は、モノの整理を超えて、
「思いやり」「自立」「家族のつながり」を育む機会にもなります。
一人で抱えこまず、できることから少しずつ、心地よい暮らしを整えていきましょう。
三世代断捨離のよくある質問(FAQ)
「親にどう声をかければいい?」「子どもに片付けをどう教える?」
3世代で取り組む断捨離には、年齢や立場ごとの悩みや疑問がつきものです。
ここでは、読者の方からよく寄せられる実用的な質問にお答えします。
不安や迷いがある方は、ぜひ参考にしてください。
A. 否定せずに「誰に残したいか」「どんな思い出か」を聞くことで、感情を整理しながら進めやすくなります。
A.年齢に合わせて、「選ぶ・残す」経験を積むことは考える力や責任感につながるためおすすめです。
A. 写真や手紙などは、デジタル化や一部保存を活用し、「残す」と「整理する」を両立させましょう。
A. 一括見積サービスなどを活用すると、比較的安価で安心な業者を選ぶことができます。
A. 会話が増えたり、家族の価値観を共有できる時間になるため、心のつながりが深まるケースも多いです。
🧐あわせて読みたい|暮らしと心の整理ヒント集

断捨離や実家の片付けを進める中で、「親が協力してくれない」「自分だけでは限界を感じる」といった悩みを感じる方も多いはず。
そんなときは、以下の記事もあわせて読むことで、家族と無理なく向き合うヒントや、心と暮らしを整える実践アイデアが見つかります。
片付け・記録・お金まわりの基本を整理。家族の合意形成まで段取りよく始められます。
👉 40代から始める“親の終活”のやさしい第一歩
世代間でずれる基準を見直し、納得感のある取捨選択を進める具体策を解説。
👉価値観の違いを越えて“本当に大切”を見つける方法
遠方・多忙でもできる支援の型を紹介。無理なく続けるコツがまとまっています。
👉 親の家サポート入門|片付け・記録・手続きの実務
罪悪感や不安への向き合い方を丁寧に解説。作業前に読んで心の負担を軽く。
👉 実家片付けで揺れる“心の整理”の始め方
言い方・順番・役割分担のコツで衝突を回避。話し合いが進みやすくなります。
👉もめないための声かけ術と合意形成
無理しない関係の保ち方や第三者の力の借り方など、心身を守る実践アイデア。
👉距離に疲れたときの“関わり方リセット”
子どもの集中と自立を育てる配置と仕組み化。三世代の暮らしにも応用可能。
👉片付けで“学び”が変わる家庭環境づくり
最初の一歩と小さな成功体験の積み重ね方を解説。巻き込みやすい順序で進みます。
👉片付けはどこから?親子で進める始め方
※この記事はプロモーションを含みます
※この記事に使用した画像の出典元は《写真AC》《Canva》です




